財務分析とは?必要性と分析方法など基本情報を解説

企業が安定した経営状態を保ちながら成長を続けるためには、定期的に経営状態を確認しておくことが重要です。
大きな問題となる前に経営の危機を把握して、対策を打ち出し、改善するにも現状把握が必要です。また、未来予測をして、経営の立て直しや、対策の方向性が正しいかどうかの判断のためにも、現状の確認は欠かせません。
そういった現状確認の手法のひとつが財務分析です。
今回は財務分析の概要や財務分析を行うために必要な諸表など、安定した経営を保つための財務分析について解説します。
財務分析とは
財務分析とはどういった分析をするものなのか、基本的な情報を確認しておきましょう。
「財務分析」をわかりやすくいうと?
財務分析とは、会社の経営を客観的で事実に基づいた数値を基に「改善点はないか」「問題点はないか」をチェックすることです。
具体的には、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表の数値を用いて、会社の収益性、安全性、生産性、成長性などを分析します。
財務分析を行うことで、経営危機を回避し、将来の利益を予測できます。さらに、正確な財務分析によって現状把握と将来予測を行うことで、経営に必要な意思決定ができるようになります。
財務分析の必要性
安定した経営を維持しつつ、戦略的に新しいプロジェクトを始動させる際には、経営危機を招かないための判断が必要です。そうした判断の基となるのが財務分析です。財務分析は、現状の経営における問題点や改善点を客観的かつ正確に把握するための重要な役割を担っています。
経営の安定化と企業の成長のために正しい判断を導くものであり、定期的に実施する必要があります。
財務分析をしないとどんなリスクがあるか
財務分析を行わないと、経営状況の把握の遅れにつながります。状況把握の遅れには下記のリスクがあります。
- 経営意思決定の質が下がる
- 将来のリスクに備えられない
- 競合他社に遅れを取る
- 経営破綻の可能性がある
企業の持続的な成長と発展のためには、定期的な財務分析が欠かせません。財務分析を怠ることは、目先の手間を惜しんで将来のリスクを招くようなものです。
財務分析の重要性を認識し、積極的に取り組んでいくべきでしょう。
財務分析に必要な3つの財務諸表
財務分析を行ううえで、「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の3つの財務諸表を理解することが不可欠です。これらの諸表は、企業の財務状況や経営成績を多角的に把握するための重要な資料となります。
1.貸借対照表
貸借対照表は、ある特定の時点における企業の財政状態を表す報告書です。企業が保有する資産、負債、純資産の残高が記載されています。
貸借対照表を分析することで、企業の資産構成や負債の状況、自己資本の充実度などを評価できます。これにより、企業の安全性や健全性を判断できます。
2.損益計算書
損益計算書は、一定期間(通常は1年間)の企業の経営成績を表す報告書です。売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益・費用、特別利益・損失などが記載され、最終的な当期純利益が算出されます。
損益計算書を分析することで、企業の収益性や効率性を評価できます。売上高の増減、売上総利益率、営業利益率などの指標を用いて、企業の収益力や費用管理の状況を把握しましょう。
3.キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、一定期間における企業の資金(お金)の流れを表す報告書です。営業活動、投資活動、財務活動の3つの区分に分けて、それぞれのキャッシュフローが記載されます。
キャッシュフロー計算書を分析することで、企業の資金繰りや投資の状況、財務戦略などを評価できます。フリーキャッシュフローなどの指標を用いて、将来の成長性や株主還元の可能性を予測することも可能です。
財務分析の5つの種類とみるべき指標
財務分析は目的によって「収益性分析」「安全性分析」「生産性分析」「成長性分析」「活動性分析」の5つの分析を行います。この5つの分析が基本的なものですが、それ以外にも、どのような情報を知りたいのかによって、さまざまな分析手法があります。
財務分析を行う際は、目的に合わせて手法を選択し、適切な指標を用いることが重要です。ここでは、基本的な5つの分析手法とその主要な指標について解説します。
1.収益性分析
収益性分析は、投下した資本に対してどれだけ効率的に利益を生み出しているかを評価するための分析です。売上高や資本に着目し、企業の「利益を生み出す力」を分析します。
指標
- 売上高総利益率(粗利率)
- 大まかな利益率を知りたいときには、売上高総利益率(粗利率)を使って分析します。粗利率は売上高に対する売上総利益の比率であり、利益率を表す基本的な指標です。
- 売上高営業利益率
- 営業活動や企業運営がどれくらい効率的に行えているかを知りたいときは、売上高営業利益率を使います。これは売上高に対して、どれくらい営業利益が残っているかを表した数字です。比率が高いほど利益が残っている状態を示しています。
- 総資本経常利益率(ROA)
- 資本に着目して、企業の総資本に対する経常利益の比率を示し、資本の有効活用度を表す指標です。
2.安全性分析
安全性分析は、企業の支払い能力や財務の健全性を評価するための分析です。流動負債や株主資本に着目し、倒産リスクの低さを分析します。
指標
- 自己資本比率
- 総資本に対する自己資本の比率を示し、長期的な経営安定性を表す指標です。
- 流動比率
- 企業が1年以内に獲得できる現預金の額を示す流動資産と、1年以内に支払う必要のある現預金の額を示す流動負債とを比較した数値が流動比率です。流動比率が小さい場合は、短期的な支払いが多いことを示しています。いいかえれば、財務の安定性は低いと考えられます。
3.生産性分析
生産性分析は、経営資源の効率的な活用度を評価するための分析です。人材、設備、資金、情報などの経営資源に着目し、それらがどれだけ効果的に売上や付加価値の創出に寄与しているかを分析します。
指標
- 労働生産性
- 労働者1人あたりの売上総利益率がどれくらいなのかを確認するときに使う指標が労働生産性です。この数値が高いほど、労働者が十分なパフォーマンスを発揮しているといえます。
- 労働分配率
- 自社が販売している商品やサービスの付加価値に占める人件費の割合を確認するときに使うのが労働分配率という指標です。労働分配率が低いと労働環境が悪いと判断されることもあります。しかし、労働分配率が高い場合には、収益を圧迫していることにもなり、利益が上がりにくい状況に陥いることも懸念されます。
4.成長性分析
成長性分析は、企業の将来的な成長可能性を評価するための分析です。売上高や利益の増加率など、将来性を多面的に分析します。
指標
- 増収率
- 前年と比べて売上高がどれくらい増減したのかを示す指標です。同じ数値でも、企業の状態(成長期なのか安定期なのか)によって、良し悪しが変わってくるので、複数年の伸び率を確認することが基本です。
- 増益率
-
前期の経常利益に比べて今期の経常利益がどれくらい増加しているかをみるための指標です。
増収率と増益率を合わせて検討することで、成長しているかどうかを判断します。 - EPS
-
1株あたりの当期の純利益を把握するときに用いる指標です。さらに、株価をEPSで割った数値(株価収益率)を指標として使うと、株価が適正であるかどうかを判断できます。
株主や投資家にとって企業の成長性は関心が集まる事項です。成長性分析によって、自社の将来性を把握するとともに、株価が適正であるかをみながら明確な基準で判断することが重要です。
5.活動性分析
在庫や固定資産を効果的に活用して売上を増やせているかどうかを確認するときに用いるのが活動性分析です。資産の回転率に着目し、それらが売上の拡大にどれだけ寄与しているかを分析します。
指標
- 棚卸資産回転率
- 適正な在庫数が管理されているかをみるための指標が棚卸資産回転率です。回転率が低いのは過剰在庫があることになるので、生産と在庫、販売がうまくいっていない可能性が示唆されます。
- 固定資産回転率
- 固定資産が有効に活用できているかを確認するときに用いる指標が固定資産回転率です。この回転率が高いほど、固定資産は効果的に活用できていることになります。
財務分析を正確に行うためのポイント
何を知りたいのかによって、それぞれの指標を基に状況を把握する財務分析ですが、正しく状況を把握するためには、正しい指標、正確な数字を用いた分析をしなくてはなりません。また、分析結果を正しく判断し、経営に活かすことも重要です。
ここでは正確に財務分析をするためのポイントをみておきましょう。
正確な財務諸表を作成する
財務分析は財務諸表の数値に基づいて行われるため、財務諸表の正確性が分析結果の信頼性を左右します。財務諸表の作成では、細かな数値の入力や取引状況の把握が必要であり、記入ミスや記入もれのないよう注意が必要です。また、会計基準の変更や新しい会計処理の適用など、最新の動向にも注意を払う必要があります。
経営戦略や目的にあった指標を使う
財務分析にはさまざまな手法と指標がありますが、分析の目的に合った指標を選択することが重要です。何を知りたいのかを明確にし、その目的に適した分析手法と指標を理解した上で、分析を行うことが求められます。
前章で解説したように、それぞれの分析にあわせて適切な指標を見るようにしましょう。
複数年の推移を見る
単年度の分析だけでは、企業の全体像を把握することは難しいでしょう。複数年にわたる財務データを比較することで、売上高や利益の増減傾向を把握し、企業の成長性や安定性を評価できます。また、複数データを比較することで、その年の数値変動が一時的なものなのか、継続的な傾向なのかも見極めやすくなります。
特に、業績の変動が大きい企業や業界では、長期的な視点での分析が重要です。景気動向なのか競合他社の動向なのか業界特有の要因を考慮した分析を行いましょう。
専門家のアドバイスを受ける
財務分析の結果をどのように解釈し、経営にどう活かすかは、専門的な知識と経験が求められます。また、分析手法や指標の選択についても、専門家のアドバイスを参考にすることで、より的確な選択が可能になります。社内に財務の専門家がいない場合は、外部の専門家や監査法人などの助言を積極的に活用することをおすすめします。
財務分析をサポートするシステムの活用を検討する
効率的かつ高精度な財務分析には、正確な数値の算出と詳細なデータに基づく考察が欠かせません。しかし、正確な分析を行うには、分析手法や指標の選択、分析結果の適切な解釈など、担当者の負担は小さくありません。財務諸表の作成から複雑な計算まで自動化できるシステムの活用を検討することで、分析業務の効率化と高度化が期待できます。
財務分析を効率化できるシステムは、日頃の取引を記録・管理したり財務諸表を作成したりできる「財務会計システム」や、財務情報だけでなく販売・生産・在庫なども総合的に管理できる「経営管理システム」などさまざまな種類があります。システムを適切に組み合わせることで、より戦略的な財務マネジメントを可能にします。
まとめ:健全な経営を続けるためにも適正な財務分析の実施を
財務分析は、企業の経営状態を客観的な数値で把握し、問題点の早期発見や適切な意思決定を行うための重要なプロセスです。財務分析を怠ると、経営状況の把握が遅れ、将来のリスクへの備えが不十分になるなど、さまざまな問題が生じる可能性があります。一方、定期的な財務分析を行うことで、自社の強みを活かした戦略の立案や、適切な経営判断が可能になります。
正確な財務分析を行うためには、財務諸表の正確性、目的に合った指標の選択、複数年の推移の確認、同業他社との比較、専門家のアドバイス、サポートシステムの活用など、いくつかのポイントに注意が必要です。
自社の状況に合わせた適切な分析手法を選択し、継続的な実践を通じて、経営の質を高めていくことが求められます。財務分析に積極的に取り組むことが、激動の時代を乗り越え、企業の未来を切り開くカギとなるでしょう。
財務分析を支える基盤の一つに、正確な財務データを管理する財務会計システムがあります。
NTTデータ関西が提供する「Biz∫ 会計」も、財務会計システム の一つの選択肢です。Biz∫ 会計は、日本の商習慣にフィットするきめ細かい機能群と法制度への迅速な対応に加え、IFRS適用やグローバルでの導入実績を持ち、お客様のグループ経営の高度化に寄与します。
Biz∫ 会計の大きな特徴は、日本基準の元帳とIFRS基準元帳を並行運用できる管理機能を持ち、複数元帳をサポートできること です。また、分析コードを自由に設定できるため、プロジェクト別の配賦、事業別・製品別の損益管理、IFRS(国際財務報告基準)対応のセグメント別会計など、お客様のニーズに応じた多様な管理・分析作業が可能となります。
財務分析の精度向上と効率化を目指す企業にとって、正確で詳細な財務データを提供するBiz∫ 会計は、強力な基盤となるでしょう。
▼ ご利用企業様のインタビュー
「ダイソー」の飛躍的な事業拡大を支えるグループ会計基盤を構築。決算早期化、業務効率化、経営情報の可視化を実現
「BIZ∫会計」の担当者インタビューもあわせてご参照ください。



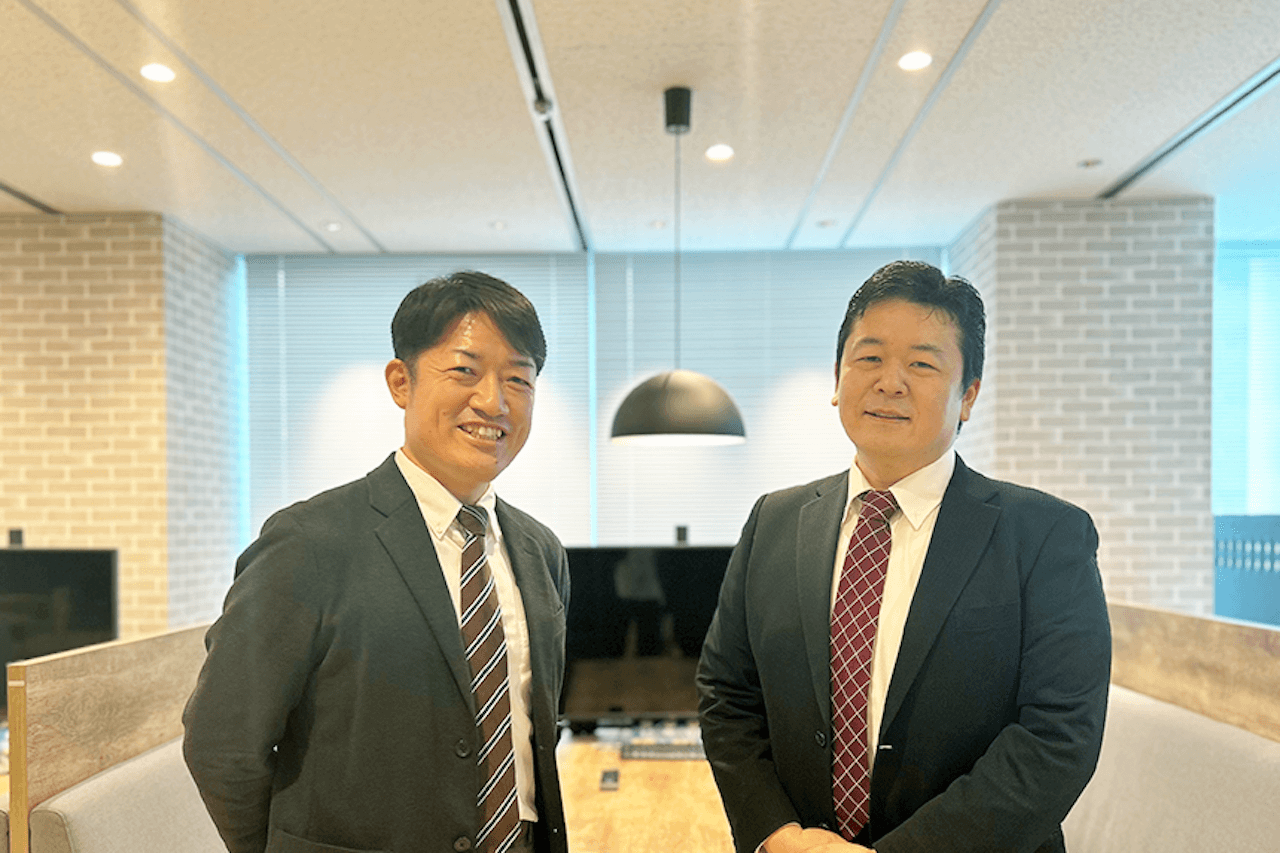


 業種から探す
業種から探す ランキング
ランキング







