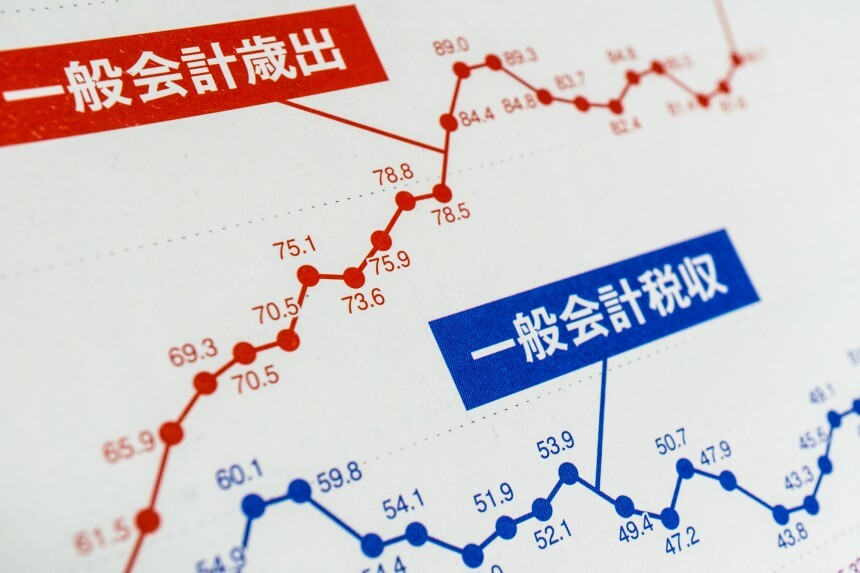脆弱性診断とは?企業にとって重要なセキュリティ対策について紹介

近年、企業を取り巻くサイバーセキュリティの環境は急速に変化しています。DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速により、ビジネスプロセスのデジタル化が進み、それに伴いサイバー攻撃のリスクも増大しています。情報システム部門やセキュリティ部門の担当者には、これまで以上に高度なセキュリティ対策が求められるようになってきました。
その中でも特に注目されているのが 「脆弱性診断」(セキュリティ診断) です。システムやネットワークの脆弱性を早期に発見し、対策を講じることは、企業の安全性を確保する上で極めて重要な取り組みとなっています。本記事では、脆弱性診断の基本から実践的なアプローチまで、セキュリティ担当者が知っておくべき重要なポイントをご紹介します。
情報セキュリティの詳細については、次の記事をご覧ください。
情報セキュリティの概要と対策の具体例とは。サイバーセキュリティとの違いも解説
DXの概要については、次の記事をご覧ください。
DX徹底解説。定義と目的、導入時の手順と課題のほか、成功事例を紹介
脆弱性診断とは
脆弱性診断は、 組織のITシステムやネットワークインフラに潜む脆弱性(セキュリティ上の欠陥)を、専門的な知識と技術を用いて体系的に検出・評価するプロセス です。この診断では、潜在的な攻撃者が悪用する可能性のあるさまざまな脆弱性を特定し、それらがもたらすリスクを評価します。
診断の対象となるのは、以下のような要素です。
- Webアプリケーションやサービス
- ネットワークインフラストラクチャ
- サーバーシステム
- データベース
- クラウドサービス
- IoTデバイス
脆弱性診断の主な目的は、 セキュリティ上の弱点を発見し、それらを修正することで組織の防御力を高める ことにあります。しかし、それだけではありません。 診断結果は、セキュリティ投資の優先順位付けや、リスク管理戦略の策定にも活用 されます。
特に重要なのは、脆弱性診断が「予防的なセキュリティ対策」という点 です。実際にインシデントが発生してからの対応では、企業の信頼性や業務の継続性に大きな影響を及ぼす可能性があります。脆弱性診断を定期的に実施することで、そうしたリスクを事前に軽減できます。
また、コンプライアンスの観点からも脆弱性診断は重要です。多くの業界標準や規制において、定期的なセキュリティ評価が求められており、脆弱性診断はその要件を満たす重要な手段となっています。
企業が抱えるリスク、脆弱性診断の重要性
進化する技術とそれに伴う脅威の複雑化
サイバー攻撃の手法は日々進化し、その複雑さは増す一方です。特に注目すべきは、ランサムウェア攻撃の深刻化です。従来のランサムウェア攻撃では、データの暗号化と引き換えに身代金を要求する手法が主流でした。しかし現在では、企業の機密データを窃取した上で、その公開を脅迫材料とする「二重恐喝」という手法も一般化しています。
実際、2022年度の国内におけるランサムウェア被害は230件に上り、前年比で84件増加しています。この数字は氷山の一角であり、報告されていない被害も相当数存在すると考えられます。
また、昨今は次のように攻撃者の手法も巧妙化しています。
- ゼロデイ攻撃: 未知の脆弱性を狙った攻撃
- フィッシング攻撃の高度化: AIを活用した精巧な偽装
- サプライチェーン攻撃: 取引先を経由した侵入
- 標的型攻撃: 特定の組織を狙った戦略的な攻撃
このような状況下で、従来型のセキュリティ対策だけでは十分な防御を確保することが困難になってきています。
サイバー空間の利用拡大に伴うリスクの増加
DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、企業のビジネスプロセスの多くがデジタル空間に移行しています。クラウドサービスやIoTデバイスの導入、リモートワークの普及により、企業のデジタル資産は急速に拡大しています。
これに伴い、以下のようなリスクが顕在化しています。
攻撃対象領域の拡大
従来のオンプレミス環境に加え、クラウドサービスやモバイルデバイスなど、保護すべき対象が増加しています。
可視性の低下
分散化したシステム環境において、すべてのセキュリティリスクを把握することが困難になっています。
新技術導入に伴うリスク
新しい技術やサービスの導入時に、セキュリティ面での検証が不十分なケースが増えています。
内部統制の複雑化
リモートワークの普及により、従来の境界型セキュリティだけでは対応が難しくなっています。
さらに、情報共有の方法も変化しています。従来のPPAP(パスワード付きZIPファイルをメールで送付する方法)は、セキュリティリスクや業務効率の観点から見直しが進んでいます。
PPAPの詳細については、次の記事をご覧ください。
PPAPとは?危険性と問題点・今後の代替案4つも紹介
脱PPAP後、資料・データの共有はどうする? ー安全と利便性を担保できる方法を探るー
脆弱性診断のプロセス
効果的な脆弱性診断は、体系的なアプローチで実施される必要があります。以下、各フェーズの詳細について説明します。
1. 検出フェーズ
検出フェーズは、脆弱性診断の出発点となる重要なステップです。このフェーズでは、組織のITインフラ全体を対象とした包括的なスキャンを実施します。この段階で重要なのは、単なる機械的なスキャンではなく、組織の特性や業務プロセスを考慮した検証を行うことです。
具体的な実施項目には、次のようなものがあります。
- 資産の棚卸しと範囲の特定
- 自動化されたスキャンツールの利用
- 手動による詳細な検証
- 新規導入システムの検証
2. 評価フェーズ
検出された脆弱性は、ビジネスへの影響度や攻撃の実現可能性などの観点から評価されます。このフェーズでは、以下の要素を考慮します。
- 脆弱性の深刻度
- 想定される被害の規模
- 修復に必要なリソース
- ビジネスへの影響
- 法規制やコンプライアンスの要件
評価結果は、CVSSスコアなどの客観的な指標を用いて数値化され、優先順位付けの基準となります。
3. 修復フェーズ
評価結果に基づいて、具体的な対策を実施していきます。このフェーズでは次のようなさまざまな対策が講じられます。特に重要なのは、修復作業による業務への影響を最小限に抑えることです。計画的な実施と、必要に応じたテスト環境での検証が求められます。
- パッチの適用
- 設定の変更
- アクセス制御の見直し
- セキュリティ機能の追加
- 運用手順の改善
4. 検証フェーズ
修復作業の完了後、その効果を確認するための検証を行います。このフェーズでは、主に次の項目が実施されます。
- 修正箇所の再テスト
- 新たな脆弱性の有無の確認
- セキュリティ対策の有効性評価
- 文書化と報告
脆弱性診断の注意点
定期的な診断の重要性
脆弱性診断は、一度実施して終わりではありません。以下の理由から、定期的な実施が必要です。
新たな脆弱性の発見
日々新しい脆弱性が発見され、それに対する攻撃手法も開発されています。定期的な診断により、これらの新しいリスクに対応できます。
システム環境の変化
システムの更新やパッチの適用、新規サービスの導入、ネットワーク構成の変更など、IT環境は常に変化しています。こうした変化に伴う新たなリスクを把握するためにも、定期的な診断が重要です。
コンプライアンス要件
多くの規制やフレームワークでは、定期的なセキュリティ評価が求められています。
継続的な改善
脆弱性診断は、セキュリティ対策の一環として継続的に改善を図る必要があります。
診断結果の分析
過去の診断結果を分析し、傾向や課題を把握します。
プロセスの最適化
診断手法や範囲、頻度などを適宜見直し、より効果的な診断を目指します。
新しい診断技術の導入
技術の進歩に合わせて、より高度な診断手法やツールを取り入れていきます。
まとめ:脆弱性診断で企業のセキュリティ体制を強化
デジタル化が加速する現代のビジネス環境において、脆弱性診断は企業のセキュリティ戦略の要となります。サイバー攻撃の手法が日々進化し、その脅威が増大する中、適切な脆弱性診断の実施は、企業の安全性を確保する上で不可欠な取り組みとなっています。
特に重要なのは、 脆弱性診断を単発の作業ではなく、継続的なプロセスとして捉えること です。定期的な診断の実施、環境変化への迅速な対応、そして診断結果に基づく継続的な改善が、効果的なセキュリティ体制の維持につながります。
また、脆弱性診断の実施には、高度な専門知識と経験が必要です。多くの企業では、内部リソースだけでは十分な対応が困難な場合があります。そのような場合、専門家による支援を受けることで、より効果的な診断と対策の実施が可能となります。
企業のデジタル資産を守り、安全なビジネス環境を維持するために、脆弱性診断の重要性を理解し、適切な実施体制を整えることが推奨されます。セキュリティ対策に不安をお持ちの方は、専門家への相談を検討されることをお勧めします。
NTTデータ関西では、専門の技術者が最新のセキュリティ対策のご提案から導入・運用まで一貫してサポートするサービスを提供 しています。セキュリティ対策にご不安をお持ちの方は、ぜひご相談ください。
▼セキュリティ導入・運用支援ソリューションの詳細について
セキュリティ導入・運用支援ソリューション| NTTデータ関西
また、下記はセキュリティ対策についての社員インタビュー記事です。「企業のセキュリティ対策」について語っていますので、ご参照ください。






 業種から探す
業種から探す ランキング
ランキング