自治体の介護DXを成功に導く実践ガイド:システム導入から運用まで

少子高齢化の進行により、自治体の介護業務は年々複雑化しています。介護保険制度の運用から事業者管理、住民サービスまで、多岐にわたる業務を限られた人員で効率的に処理することが求められるなか、デジタル技術の活用は避けて通れない課題となっています。
本記事では、自治体における介護DXの全体像から具体的な導入手法、システム選定のポイントまで、実務担当者が直面する課題に対応した実践的なアプローチを詳しく解説します。
目次
自治体における介護DXとは
介護DXとは、デジタル技術を活用して介護保険業務や関連する行政サービスを変革し、効率性と利便性を向上させる取り組みです。単なるシステム導入ではなく、業務プロセス全体を見直し、住民と事業者双方の負担軽減を実現する包括的な改革を指します。
厚生労働省では2021年度から「介護DX推進戦略」を掲げ、全国の自治体に対してデジタル化の加速を促しています。特に介護保険関連業務では、申請・認定・給付の各段階でのデジタル化により、処理時間の短縮と正確性の向上が期待されています。
自治体が直面している介護業務の課題
現在の介護保険業務では、紙ベースの申請処理や手作業による審査が多く、業務負荷の増大が問題となっています。要介護認定の申請から結果通知までに要する期間の短縮、ケアマネジャーとの連携強化、介護事業者への指導監督業務の効率化など、解決すべき課題は山積しています。
また、住民からは24時間いつでも利用できるオンラインサービスへの期待が高まっている一方で、高齢者のデジタルデバイド(デジタル技術を利用できる人とできない人との格差)対策も重要な検討事項です。利便性向上と誰もが使いやすいサービス提供の両立が求められています。
介護認定調査の効率化については、次の記事で詳しく解説しています。
介護認定調査の質を高める「チェックシート活用術」―自治体担当者が知るべき業務標準化の秘訣
介護DX推進によるメリットと効果
介護DXの推進により、自治体は複数の重要な効果を得ることができます。まず、申請処理時間の短縮により職員の負担軽減と住民満足度の向上を同時に実現できます。
コスト削減効果も大きな魅力です。紙の削減、郵送費の軽減、人的作業時間の短縮により、年間数百万円から数千万円のコスト削減を実現した自治体も報告されています。
サービス品質の向上では、システム化によるヒューマンエラーの防止、一貫した審査基準の適用、迅速な情報提供が可能になります。住民と事業者双方から高い評価を得られる質の高いサービス提供が実現できます。
国の政策動向と自治体に求められる対応
政府の介護DX推進政策は急速に進展しており、自治体には段階的かつ確実な対応が求められています。デジタル庁と厚生労働省が連携して策定した工程表に基づき、各自治体は計画的な取り組みを進める必要があります。
介護DX推進に関する法令・ガイドライン
介護保険法の改正により、自治体には介護給付等費用適正化事業の実施が義務付けられています。この中で、ICTを活用した効率的な業務運営と適正化の推進が明確に位置づけられました。
「自治体DX推進計画」では、介護分野における優先的取組事項として、介護保険関連業務のデジタル化が重点項目に指定されています。2025年度までに全国の自治体での標準準拠システムへの移行が目標とされており、対応遅れは住民サービスの低下につながるリスクがあります。
個人情報保護法やマイナンバー法との整合性確保も重要な要素です。介護データの適切な取り扱いと利活用のバランスを保ちながら、法令遵守の徹底が不可欠になります。
標準化・共通化の動向
共通化されたサービスの提供と事業者負担軽減の観点から介護保険システムの標準化が推進されています。標準仕様書に基づくシステム構築により、自治体間でのデータ連携や事業者の複数自治体対応が円滑になります。
これと並行してAPI連携の標準化も進められており、既存システムとの接続性向上や段階的な移行が可能になります。一度にすべてを変更するのではなく、重要度の高い機能から順次更新することで、業務継続性を確保しながらデジタル化を進められます。
さらに、これらの標準化の基盤としてクラウドファーストの原則に基づき、多くの標準システムはクラウド環境での提供が前提となっています。セキュリティ対策とコスト最適化を両立させた運用が期待されます。
補助金・支援制度の活用
介護DX導入において、国の補助金制度を効果的に活用することで、財政負担を大幅に軽減できます。主要な支援制度の概要は以下の通りです。
| 補助金制度 | 管轄省庁 | 補助率 | 対象範囲 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| デジタル田園都市国家構想交付金 | デジタル庁 | 最大75% | システム導入費用 | 介護DX関連への手厚い支援 |
| 自治体DX推進交付金 | 総務省 | 事業により異なる | 複数年度対応可能 | 段階的なデジタル化を支援 |
| 介護保険事業費補助金 | 厚生労働省 | 事業により異なる | 認定・給付適正化システム | 介護保険特別会計での予算確保 |
デジタル田園都市国家構想交付金では、介護DX関連の取り組みに対して手厚い支援が用意されています。システム導入費用の最大75%が補助対象となるケースもあり、積極的な活用により財政負担を大幅に軽減できます。
総務省の自治体DX推進交付金は、複数年度にわたる計画的な投資により、段階的なデジタル化を進められる点が特徴です。申請手続きや要件確認は複雑ですが、早期の情報収集と計画策定により確実な採択を目指すことができます。
厚生労働省の介護保険事業費補助金では、要介護認定の適正化や給付適正化に資するシステム導入が支援対象となっています。既存の介護保険特別会計の枠組みを活用した効率的な予算確保が可能です。
デジタル田園都市についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
デジタル田園都市国家構想とは?目的やポイント・4つの事例をわかりやすく解説
住民サービス向上のための機能設計
介護DXの最終目的は、住民により良いサービスを提供することです。利用者の視点に立った機能設計により、利便性の向上と職員の業務効率化を両立させることが重要になります。
オンライン申請システムの構築
介護認定の新規申請や更新申請をオンラインで受け付けるシステムにより、住民は24時間いつでも申請が可能になります。必要書類の電子添付機能、申請状況の確認機能、自動確認メール送信など、利用者の利便性を重視した設計が重要です。
入力フォームの使いやすさはシステムの利用率に直結します。分かりやすい項目名、入力ミス防止機能、一時保存機能など、高齢者でも安心して利用できるインターフェースの実現が必要です。
スマートフォンやタブレットからの利用を想定したレスポンシブデザインにより、多様なデバイスからのアクセスに対応します。外出先や施設からでも簡単に申請できる環境を提供できます。
オンライン申請システムについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
申請管理システムで自治体DXを加速。導入効果と選定ポイントを解説。
窓口業務のデジタル化
窓口での本人確認や申請内容の確認をデジタル化することで、手続き時間の短縮と正確性の向上を実現できます。マイナンバーカードの読み取り機能、電子署名の活用により、従来の書面確認作業を大幅に簡素化できます。
待ち時間の短縮とサービス品質向上のため、予約制度の導入やリアルタイムの混雑状況表示機能も効果的です。住民は空いている時間帯を選んで来庁でき、職員も計画的な業務遂行が可能になります。
多言語対応機能により、外国人住民へのサービス向上も図れます。自動翻訳機能や多言語での音声案内により、言語の壁を越えたサービス提供が実現できます。
窓口業務の効率化については、次の記事も参考にしてください。
窓口DXで実現する住民サービス改革 ~先進事例に学ぶ、効果的な自治体DX推進のポイント~
利用者支援とデジタルデバイド対策
高齢者向けの操作支援機能として、大きな文字表示、音声読み上げ機能、シンプルな画面構成などの配慮が必要です。また、操作に不安がある方向けの電話サポートや窓口でのサポート体制も重要な要素です。
デジタル機器の操作に慣れていない住民向けの講習会やサポート制度により、誰もがデジタルサービスの恩恵を受けられる環境を整備します。地域のボランティアや民生委員との連携も効果的です。
従来の紙ベースでの手続きも並行して維持し、住民が選択できる環境を提供することで、デジタル化による利便性向上と従来手法での安心感の両立を図ります。
データ連携と標準化への対応
介護DXの成功には、庁内システム間のデータ連携と標準規格への準拠が不可欠です。既存システムとの整合性を保ちながら、将来的な拡張性を確保する設計が求められます。
既存システムとの連携
住民基本台帳システムとの連携により、介護保険被保険者情報の自動更新と整合性確保が可能になります。転入・転出処理や住所変更などの基本情報変更を自動反映することで、データの正確性向上と職員の作業負荷軽減を実現できます。
財務会計システムとの連携では、介護保険料の収納管理と給付費支払いの効率化が図れます。リアルタイムでの収支状況把握により、適切な財政管理と予算執行が可能になります。
さらに、地域包括支援センターや介護事業者が利用する情報共有システムへの接続により、一体的なサービス提供が実現できます。重複する情報収集を避け、利用者にとって使いやすいサービス環境を構築できます。
マイナンバー連携の活用
マイナンバー情報連携基盤の導入により、他自治体や関係機関との情報連携業務が大幅に効率化されます。現在多くの自治体で課題となっている転入者の前住所地での介護保険情報取得や医療保険者との給付調整業務の自動化が実現しつつあります。
マイナポータルとの連携は段階的に進められており、住民が自らの介護保険情報を確認するセルフサービス機能の提供が始まっています。認定結果の通知確認、サービス利用状況の照会、申請進捗の確認など、従来は電話や窓口での問い合わせが必要だった業務の一部がオンライン化されています。
デジタル証明書を活用した本人確認プロセスの簡素化については、技術的な課題とコスト面での検討が必要な状況です。導入済みの自治体では窓口での書類確認作業の軽減効果が報告されていますが、全面的な展開には時間を要する見込みです。
NTTデータ関西では、住民からの電子申請の受付やマイナンバー連携を含む一連の手続きを一元管理できる電子申請システム「e-TUMO(イーツモ)」を提供しています。マイナンバーカードによる安全な本人確認機能を搭載し、申請受付から審査まで電子申請システム上で実施することで、住民と自治体双方の利便性向上を支援します。
セキュリティ対策とプライバシー保護
個人情報保護法に基づく適切なデータ管理体制の構築が必要です。アクセス権限の厳格な管理、操作ログの記録・監視、定期的な監査の実施により、情報漏えいリスクを最小限に抑えます。
管理体制と合わせて、技術的なセキュリティ対策も不可欠になります。暗号化技術の活用により、データの保管時と通信時の両方でセキュリティを確保します。最新の暗号化基準に準拠したシステム設計により、長期的な安全性を維持できます。
さらに、システムの継続性確保も重要なセキュリティ要素の1つです。災害時のデータ保護とシステム継続性確保も重要な要素です。クラウド環境の活用やデータバックアップの多重化により、非常時でも業務継続可能な体制を構築します。
BCP(事業継続計画)対策やクラウド活用などの詳細については次の記事も参考にしてください。
BCP対策とは何をどうすればよいのでしょうか? 企業や自治体に必要な事業継続計画の策定手順と運用方法
システム選定と導入プロセスの実践手法
介護DXシステムの選定では、自治体の規模や既存システムとの整合性、将来的な拡張性を総合的に評価することが重要です。適切な選定プロセスを経ることで、導入後の運用トラブルや追加コストを最小限に抑えられます。
要件定義と仕様書作成
システム要件の整理では、現行業務の詳細な分析から始めることが基本です。介護保険業務の各プロセスにおける処理時間、処理件数、関連する帳票類、他システムとの連携要件を具体的に把握します。
機能要件の定義では、必須機能と付加機能を明確に分類し、優先順位を設定します。限られた予算から最大の効果を得るため、段階的な導入計画との整合性も考慮に入れます。
非機能要件では、システムの可用性、拡張性、セキュリティ要件を詳細に規定します。特にセキュリティ要件は、個人情報保護の観点から厳格な基準を設定する必要があります。
ベンダー選定の評価基準
技術力の評価では、自治体向けシステムの開発実績と介護保険制度への理解度を重視します。法改正への対応実績、他自治体での導入事例、システムの安定性などを総合的に判断します。
サポート体制の充実度も重要な選定要因です。導入時の支援体制、運用開始後の保守対応、法改正時のシステム更新対応など、長期的なパートナーシップを見据えた評価が必要です。
コスト構造の透明性と妥当性も慎重に検討します。初期導入費用だけでなく、年間保守費用、カスタマイズ費用、将来的なバージョンアップ費用まで含めた総保有コストで比較することが重要です。
導入スケジュールと体制構築
プロジェクト体制では、庁内の関係部署との連携体制を早期に確立します。介護保険担当部署、情報システム部署、財政部署の密接な協力により、スムーズな導入を実現できます。
段階的な導入計画により、業務への影響を最小限に抑えながら確実な移行を進めます。重要度の高い基幹機能から順次稼働させ、運用状況を確認しながら機能を拡張していく方法が効果的です。
職員研修と習熟期間の確保も導入成功の重要な要素となります。システム操作の習熟だけでなく、新しい業務プロセスへの理解促進により、導入効果を最大化できます。
予算計画と投資対効果の測定
介護DXシステムの導入では、初期投資と継続的な運用コストを総合的に評価し、中長期的な視点での投資対効果を測定することが重要です。限られた予算の中で最大の効果を得るため、戦略的な投資計画が必要になります。
NTTデータ関西では、介護認定調査から訪問調査後までの一元の業務を効率化する介護認定支援アプリ「ねすりあ」を提供しています。アプリを活用することで、これまでの手書きによる記入ミスの防止、調査時間の短縮、データ入力作業の削減により、調査員の負担軽減と認定業務の迅速化を同時に実現します。段階的なデジタル化の起点として投資対効果の高い導入が可能です。
コスト構造の理解と予算確保
システム導入の初期費用は、ソフトウェアライセンス、ハードウェア、導入支援、職員研修の4つの要素で構成されます。クラウドサービスを利用する場合は、従来のオンプレミス型と異なり、初期費用を抑えて月額制・年額制・従量課金制など柔軟な料金体系での運用が可能になります。
年間運用費用では、システム保守費、クラウド利用料、職員の維持管理作業に要する人件費を正確に見積もる必要があります。多くの場合、導入後3年程度でペイバック期間を迎え、それ以降は継続的なコスト削減効果が期待できます。
法改正対応費用も重要な予算項目です。介護保険制度は3年ごとに大きな見直しが行われるため、その都度システム改修が必要になります。年間保守費用に含まれる場合と別途費用が発生する場合があるため、契約時の確認が重要です。
ROI測定の具体的手法
業務効率化による人件費削減効果を定量的に測定します。介護認定申請の処理時間短縮、事業者指導業務の効率化、住民対応時間の軽減などを時間単位で算出し、職員の時間単価を掛け合わせることで削減効果を数値化できます。
紙やファイリング費用、郵送費などの直接的なコスト削減も重要な効果指標です。年間の消耗品費や通信費の削減額を正確に把握し、継続的な効果を測定します。
住民満足度の向上効果は定量化が困難ですが、アンケート調査やサービス利用率の向上により間接的に評価できます。デジタルサービスの利用促進により、窓口混雑の緩和や待ち時間短縮などの効果も期待できます。
段階的投資による効果最大化
重要度の高い機能から優先的に導入することで、早期の効果実現と予算の分散化を図れます。介護認定管理システムから開始し、給付管理、事業者管理、住民向けサービスの順に展開する方法が一般的です。パイロット導入により、小規模な範囲でシステムの有効性を検証してから本格展開を行う方法も効果的です。一部の地域や特定の業務に限定した試行運用により、課題の早期発見と改善が可能になります。
他自治体との共同調達や広域連携により、導入コストの削減と効果の共有を図ることも可能です。近隣自治体との協力により、スケールメリットを活用した効率的な導入を実現できます。
将来展望とさらなる発展可能性
介護DXは単なるシステム導入にとどまらず、自治体の行政サービス全体の変革につながる可能性を秘めています。AI技術やデータ活用の進展により、予防的な介護政策や個別最適化されたサービス提供など、新たな価値創造が期待されます。
AI・データ分析の活用展望
蓄積された介護保険データの分析により、地域の介護ニーズ予測や効果的な政策立案が可能になります。人口動態や疾病構造などの多面的な分析により、将来の介護需要を高精度で予測し、計画的な施設整備や人材育成に活用できます。
要介護認定においても、AIを活用した審査支援システムの導入が期待されています。過去の認定事例と医学的知見を学習したAIが主治医意見書や調査票の内容から適切な要介護度を提案し、審査の一貫性向上と処理時間短縮を実現します。
現在、調査データの整合性確認においてもAIの活用が進んでいます。前述の介護認定支援アプリ「 ねすりあ 」では、調査項目間の矛盾や記入漏れをAIが自動で検出し、調査員による目検時間を大幅に短縮しています。このような現場レベルでのAI活用により、認定プロセス全体の品質向上と効率化が実現されています。
データ分析へのAIの活用については、次の記事も参考にしてください。
AIによるデータ分析を使いこなすには?メリットや重要性、活用手法を徹底解説
広域連携と共同利用の拡大
複数の自治体による共同システム運用は、単独導入が困難な小規模自治体にとって特に有効な選択肢です。システム開発費用の分散により、先進的な機能を持つシステムを導入できる一方、運用ノウハウの共有や障害対応の相互支援により、安定的なサービス提供も実現できます。
このような広域連携のさらに発展的な取り組みとして、介護人材の広域マッチングシステムの構築が注目されています。地域を越えた効率的な人材活用により、資格や経験に基づく適切なマッチング、研修機会の共有、キャリア形成支援など、人材不足の解決に向けた包括的な取り組みが可能になります。
データ連携基盤の整備が進むことで、自治体間でのベンチマーキングや政策効果の比較分析も容易になります。類似の地域特性を持つ自治体との比較により、効果的な政策立案と継続的な改善を推進でき、介護DXの効果をより高められる環境が整いつつあります。
持続可能な運用体制の構築
職員のデジタルスキル向上と組織文化の変革で、継続的な改善と発展を実現する体制構築が重要です。定期的な研修制度、他自治体との交流、先進技術の情報収集などにより、変化する環境に対応できる組織能力を維持します。
一方、システムを実際に利用する住民の視点も忘れてはなりません。住民参加型のサービス改善により、利用者のニーズに応じた継続的な機能向上を図ります。定期的なアンケート調査、利用状況の分析、住民との対話の場を通じて、真に必要とされるサービスの提供を実現します。
技術的な側面では、技術革新への対応と長期的な投資計画により、持続可能なシステム運用を確保することが不可欠です。クラウド技術の進化、セキュリティ対策の高度化、新たな法制度への対応など、変化する環境に柔軟に適応できる体制を構築することが重要です。
まとめ:介護DXで実現する住民中心の行政サービス
介護DXは自治体にとって避けて通れない重要な課題であると同時に、住民サービス向上と業務効率化を同時に実現する大きなチャンスでもあります。適切な計画と段階的な実装により、限られた資源でも大きな成果を得ることが可能です。
成功のポイントは、技術導入だけでなく業務プロセス全体の見直しと職員の意識改革にあります。住民の立場に立ったサービス設計と、持続可能な運用体制の構築により、長期的な価値創造を実現できます。
計画的なアプローチと他の自治体との連携により、地域の特性に応じた最適解を見つけることが重要です。外部専門家の活用や補助金制度の積極的な利用により、効率的で確実な導入を進めることができるでしょう。
NTTデータ関西では、要介護認定者への訪問調査から調査票作成までの一連の業務を効率化し、迅速かつ正確に行うことができる専用アプリ「 ねすりあ 」を提供しています。紙の調査票をタブレット端末での入力に置き換え、AIや豊富な入力補助機能により、業務負担やミスを大幅に軽減します。訪問調査の現場から最終的な調査票完成まで、認定業務全体の迅速化と正確性向上を支援いたします。




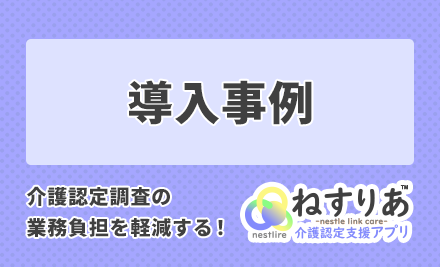

 業種から探す
業種から探す ランキング
ランキング







