企業成長の鍵を握るリスキリングとは?成功までの完全ガイド

リスキリングとは、変化する仕事の要件に適応するために、従業員が新しいスキルを習得することです。 急速に変化するビジネス環境で企業が競争力を維持・向上させるための重要な戦略の一つ です。
本記事では、リスキリングの概要から導入手順、成功のポイントまでを詳しく解説します。本ガイドを参考にリスキリングを実践することで、従業員のスキルアップと組織の競争力向上を同時に実現できるでしょう。
人事担当者や経営層の皆様に、組織変革の新たな視点をお届けします。
目次
リスキリングとは
経済産業省の「デジタル時代の人材政策に関する検討会」によると、 リスキリングとは「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」 と示されています。
単なるスキルアップとは異なり、リスキリングは現在の職務とは大きく異なる新しい役割や職種に対応するためのスキル開発を含みます。多くの場合、従業員が個人的にスキルアップをするのではなく、企業が自社の従業員に向けて学ぶ機会を提供するというものです。急速に変化するビジネス環境において、リスキリングは組織の競争力を維持・向上させるための重要な戦略となっています。
似た言葉に「リカレント」「OJT」があります。その違いを確認しておきましょう。
リカレント教育との違い
リカレントというのは「生涯学習」とも呼ばれ、自分の持っているスキルを磨きながら、新たな学びによってプラスアルファのスキルを身につけることを意味しています。
リスキリングとリカレント教育は、どちらも社会人が新たなスキルを習得するという点では共通しています。
一方で、両者はスキルアップをする目的や実施タイミングが異なります。リスキリングは、企業が従業員に対して新しいスキルを習得させることを目的としているのに対し、リカレント教育は、個人が主体となって行う学び直しのプロセスを指します。
そのため、リスキリングは、デジタル技術の進展やDX推進のタイミングで行われますが、リカレント教育を実施するタイミングの多くは、個人が転職を考えたときや新たな業務を担当したいと思った時がほとんどです。
OJTとの違いとは
OJTというのはOn the Job Trainingの略で、新入社員や未経験者が、実務を通して仕事の手順や注意点などを経験的に学ぶ仕組みのことを指します。OJTでは、先輩社員のやり方や現場の雰囲気を体感しながら実務を経験することによって、仕事を完遂させるために必要な技術のみならず、周りとの連携や配慮の必要性といった現場組織のやり方・常識とされている考え方も含めて学べます。
リスキリングとOJTは、どちらも企業内でのスキル習得の手法の一つです。
異なるのは、リスキリングは既存の業務に関連せず新たなスキルを習得するのに対し、OJTは現状の部署や業務に関連する業務のスキルアップを目指す点です。
リスキリングが注目されている背景
リスキリングが注目を集める背景には、以下のような要素が絡み合っています。
- 急速な技術革新
- 雇用の流動化
- 人材不足の深刻化
- グローバル競争の激化
- コスト効率の追求
- 国からのリスキリング支援強化
AIやIoTなどの新技術の台頭により従来の業務プロセスや必要スキルが急速に変化しました。また、終身雇用制度の崩壊や働き方の多様化により個人のキャリアパスが多様化したこともリスキリングが注目されるようになった要因の一つです。
さらに、グローバル競争や少子高齢化など、社会的要因もリスキリングの注目度に大きな影響を与えています。
また、国からのリスキリング支援としては、経済産業省の 「リスキリングを通じたキャリアアップ事業」 が挙げられます。キャリア相談やリスキリング講座の受講、補助金までさまざまな支援を受けられます。
このような要因が組み合わさり、今後もリスキリングへの注目度はさらに高まっていくのではないでしょうか。
企業がリスキリングに取り組むメリット
企業が、コストをかけてでもリスキリングに取り組む理由はどこにあるのでしょうか?
リスキリングのメリットは以下の4つです。
- 業務効率化
- イノベーションの促進
- コスト削減
- 人材流出の回避
一つずつ解説していきます。
業務効率化
リスキリングを通じて従業員が新しいスキルを習得することで、業務プロセスの効率化が進みます。
例えば、デジタルツールの活用スキルを向上させることで、従来の手作業が自動化され、生産性が大幅に向上する可能性があります。また、新しい技術や手法を学ぶことで、従来の業務の無駄を発見し、改善することも可能になります。
イノベーションの促進
新しい知識やスキルを持つ従業員が増えることで、組織全体の創造性が高まり、イノベーションが促進されます。異なる分野のスキルを組み合わせることで、新しいアイデアや解決策が生まれやすくなるでしょう。
また、最新の技術トレンドに精通した従業員が増えることで、新製品・サービスの開発や既存ビジネスモデルの革新につながる可能性も高まります。
イノベーションの概要や種類、成功事例は以下の記事をご参照ください。
イノベーションはどうやって起こす?必要なこと、成功事例を紹介
コスト削減
リスキリングは、新規採用に比べてコスト効率が高くなる傾向にあります。
既存の従業員を育成することで、採用活動や新入社員の教育にかかるコストのほか、業務効率化によって人件費や運営コストの削減にもつながります。長期的には、組織全体の生産性向上によって、より大きなコスト削減効果が期待できます。
人材流出の回避
リスキリングは従業員の満足度とエンゲージメントを高める効果があります。キャリア開発の機会を提供することで、従業員の成長意欲に応え、組織への帰属意識を高めやすくなるでしょう。
これにより、優秀な人材の流出を防ぎ、長期的な人材確保につながります。また、企業のリスキリングへの取り組みは、人材市場における企業の評価にもポジティブな影響を与え、優秀な人材の獲得にも寄与します。
リスキリングを進める手順
リスキリングを進める際は、以下の4ステップで進めることをおすすめします。
- 組織のスキルレベルの現状とゴール設定
- リスキリングプログラムの設計
- プログラム実施の提案
- プログラム実施とモニタリング
全体像を把握して、スムーズに導入を進めましょう。
1.組織のスキルレベルの現状とゴール設定
リスキリングを始める前に、まず組織全体のスキルレベルの現状を把握し、将来的なゴールを設定することが重要です。現在の従業員のスキルを評価し、業界動向や技術トレンドを分析して、将来必要となるスキルを予測します。
この現状とゴールのギャップを明確にすることで、効果的なリスキリング計画を立てやすくなります。ゴールの例としては「DX人材の育成」や「 クラウド テクノロジーの習得」「サイバーセキュリティ対応力の強化」などが当てはまります。
これらのゴールを設定する際は、組織の戦略や事業計画と整合性を取るようにしましょう。
DX人材の概要は以下の記事をご参照ください。
2.リスキリングプログラムの設計
ゴールが設定されたら、具体的なリスキリングプログラムの設計です。
学習内容や学習方法、スケジュール、必要なリソースなどを詳細に計画します。eラーニング、集合研修、OJT、外部セミナーなど、さまざまな学習方法を組み合わせることで、効果的な学習環境を創出できるでしょう。また、個々の従業員のニーズや学習スタイルに合わせて、カスタマイズされたプログラムを提供することも検討しましょう。
3.プログラム実施の提案
設計したプログラムを従業員に提案する際は、リスキリングがもたらす個人的なメリットを明確に伝えることが重要です。キャリアの安定性向上、新たな挑戦の機会、自己成長の実感、収入増加の可能性など、従業員それぞれにとってのメリットをアピールしましょう。
また担当者が推進する場合は、経営層に対しても、ビジネス面でのメリットを強調する必要があります。生産性向上と業務効率化が収益性の改善につながることを示しましょう。人材採用・育成コストの削減効果や、従業員の定着率向上による人材流出リスクの軽減なども重要なポイントです。
従業員と経営層それぞれの視点に立ったメリットを明確に伝えることで組織全体からリスキリングへの理解と支持を得やすくなります。手間はかかりますが、プログラムの円滑な実施につながる重要な取り組みです。
4.プログラム実施とモニタリング
プログラムの実施段階では、進捗状況を定期的にモニタリングし、必要に応じてサポートを提供することが重要です。学習の効果を測定し、フィードバックを収集して、プログラムの改善に活かします。
また、成功事例を共有したり、達成を称える機会を設けたりすることで、組織全体のモチベーションを維持・向上させることも可能です。
リスキリングを成功させるためのポイント
リスキリングを成功させるポイントは、以下の2つです。
- 外部の専門組織の活用も検討する
- 継続的にリスキリングを実施する
コツをおさえて、効率的に導入を進めていきましょう。
外部の専門組織の活用も検討する
リスキリングに必要なスキルや教育カリキュラム、プログラムの作成は、社内だけで行うと時間や費用などのコストがかさむ可能性があります。
特に、ノウハウが不足している場合は、求めるスキルを学ぶための適切なカリキュラムやプログラムの編成が困難になることもあります。そこで、外部の専門組織を活用し、講師を招いたり、コンテンツの提供を受けたりすることで、コスト削減と効率的なリスキリングの実現が可能になります。
また、専門家のアドバイスを受けることで、自社に最適なスキルを効果的に習得するための方策を見出しやすくなるでしょう。
継続的にリスキリングを実施する
リスキリングは新たなスキルを身につけるプロセスであり、一度きりの取り組みでは十分な効果を得ることは難しいでしょう。実際に使えるスキルが身についているか、業務効率や生産性はどう変化したかを、実践を通じて確認しながら進めていく必要があります。
また、リスキリングのプログラムについても、社員の声を聞きながら継続的に改善を図り、より学びやすいカリキュラムや、個別化されたプログラムへと発展させていくことが大切です。
リスキリング実施の事例
では、具体的にリスキリングを行った事例を見てみましょう。
「デジタル人財」化計画として学び合いで全社員を育成:NTTデータ
NTTデータは、デジタル変革を推進する人材を「デジタル人財」と位置づけ、以下のように3つに分類しました。
- デジタル活用人材:デジタルサービスをビジネスに結びつける役割
- デジタル専門人材:先進デジタル技術を用いてサービスを創出する役割
- デジタルコア人材:先進デジタル技術を開発する役割
これら3つの人材が連携することで、顧客に新しい価値を提供することを目指しています。
具体的な取り組みとしては、まず「技統本塾」を設立しました。これは技術革新統括本部のトップ技術者が塾長となり、若手・中堅社員を半年間マンツーマンで教育する徒弟制度的な仕組みです。
また、ADP(Advanced Professional)制度を導入しました。この制度は、先進技術領域で卓越した専門性を持つ人材を外部から採用するものです。さらに、高度な専門性を獲得した社員の会社への貢献度に応じて報酬を決定する制度「TG(Technical Grade)制度」も実施しています。
これらの施策により、NTTデータの社員は実際のビジネスをこなしながら技術やスキルを高められる環境を整備し、多様なスキル・パフォーマンスの発揮を促進しています。
まとめ:リスキリングで世界に通用する企業を目指す
リスキリングは、急速に変化するビジネス環境において、企業の競争力を維持・向上させるための重要な戦略です。技術革新や雇用の変化に対応し、組織の生産性を高め、イノベーションを促進する効果があります。
リスキリングを成功させるためには、組織の現状と目標を明確にし、効果的なプログラムを設計・実施することが重要です。また、従業員や経営層それぞれにメリットを明確に伝え、理解と指示を得られるよう働きかけるようにしましょう。



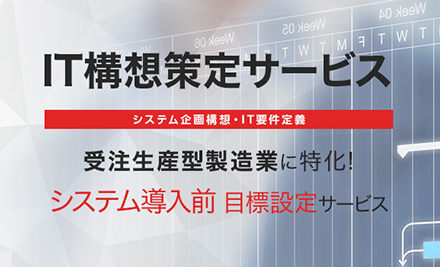


 業種から探す
業種から探す ランキング
ランキング







