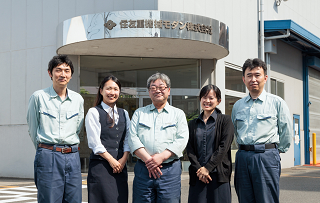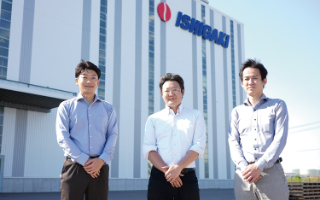30年来運用してきたスクラッチ開発の
生産管理システムを刷新
データドリブンによる製造現場の
業務改革が大きく前進
電力・環境エネルギー分野をコア事業として情報と制御の独創技術を展開し、OT・IT・プロダクトの3つすべてを有する強みを発揮している正興電機製作所。現在は、カーボンニュートラルを実現する蓄電システムや小水力発電システム、AI搭載のロボット、カメラ、DX事業、健康経営支援ソリューションなど多角化を進めています。そんな同社ですが、約30年前にスクラッチ開発で導入し、現在まで使い続けてきた生産管理システムが限界を迎えていました。
そこでNTTデータ関西の「BIZXIM製番」を導入して生産管理システムを刷新し、データドリブンによる製造現場の業務改革を推進。さらに今後は、E-BOMとM-BOMを緊密に連携させたデータ活用により、受注から出荷までトータルに見渡すことができる生産管理システムの実現を目指しています。
課題
約30年前にスクラッチ開発し、使い続けてきた生産管理システムは、何世代にもわたる改修を重ねてきたため、アップデートが限界にきており、日々の運用にも不安が残る。
継ぎ接ぎによって実装されてきた非効率な業務プロセスが、そのままの形でシステムに内在。
効果
データドリブンによる業務改革
- バーコードを通じて工程間のデータを受け渡し、そのデータを全社で共有することで、各製品の生産状況を一元的に把握・管理。
生産管理システムの保守メンテナンス業務から解放
- BIZXIM製番の基本的な管理はすべてNTTデータ関西側で行われるため、高く信頼のおける安心な運用を実現。
生産管理システムの刷新に踏み切った背景は?
- 山崎氏
当社において生産管理システムの再構築が急務となった理由は、端的に言えば既存の生産管理システムの老朽化です。
約30年前にスクラッチ開発し、現在まで使い続けてきたもので、サーバーのOSにしても、データベースにしても、何世代にもわたってバージョンアップを重ねながら、それにあわせる形でシステムの改修を繰り返してきました。しかし、そうした改修ももはや限界に達していました。- 吉川氏
IT部門として生産管理システムの保守メンテナンスを担っていますが、果たして次回のWindowsのバージョンアップに耐えられるのだろうか、それ以前に随時行われる機能アップデートやセキュリティパッチを適用した時点でシステムが止まってしまうのではないか、といつも不安を抱えていました。
- 山崎氏
そんなIT部門の頑張りによって、なんとかシステムは今日まで持ちこたえてこられたのですが、そうした中で生産管理システムは、より根深い問題も抱えていました。
当社は電力の安定供給をサポートする監視制御システムやデジタル化制御システム、配電機器などをコア技術として、近年はIoT技術を応用したシステムや次世代型の系統運用システム、水処理監視制御システム、家庭用蓄電システム、特殊電源装置、スイッチのON/OFFで透明と白濁を瞬時に切り替える調光フィルムなど多岐にわたる製品を手がけており、各製造現場からは生産管理システムに対して新たなニーズが次々に出てきます。
IT部門は保守メンテナンスだけでなく、こうしたカスタマイズや機能追加の要求にも100%に近い形で応えてくれており、おかげで各製造部門は問題なく日々の業務を遂行できています。ただ、それがゆえに私たちは多くの問題を先延ばしにしてきたことが否めません。過去から継ぎ接ぎでシステムに実装されてきた非効率な業務プロセスを、そのまま現在まで引きずってきました。
BIZXIM製番を選定した経緯
- 山崎氏
あらゆる観点から既存の生産管理システムに限界を感じていた中、経営層から直々に「システムを再構築せよ」という指示が下りました。もっとも既存の生産管理システムの機能をそのまま継承する形で再開発するとなれば、莫大なコストがかかることは経営層も認識しており、「今回はスクラッチ開発ではなく、世の中に汎用的なパッケージとして出回っているソフトウェア製品を活用すべき」という条件があわせて示されました。
これが生産管理システム再構築プロジェクトのスタートとなり、すぐに製品選定に入りました。基本方針としたのは、工程管理だけにフォーカスするのではなく、受注から出荷までBOM(部品表)を軸にトータルに見渡すことができる生産管理システムの実現です。
また、システムが提供する標準機能に自分たちの業務をあわせることで、無駄なプロセスを排除してモノづくりの体制そのものを変革することを目指しました。- 吉川氏
山崎さんが中心となって打ち出した新たな生産管理システムの基本コンセプトに基づき、まずはWebを通じて製品調査を開始しました。
個別受注生産を基本としつつ仕込み生産(見込み生産) にも対応し、なおかつクラウド型のサービスとして利用できることを前提条件として候補となるソフトウェア製品をリストアップしました。さらに様々な原価諸元(部品表、歩留、生産性、原単位など)で計算ができること、常備品の発注点管理ができることといった詳細な条件を加味しながら、絞り込んでいきました。- 山崎氏
こうして最終候補に残ったNTTデータ関西のBIZXIM製番と外資系パッケージの2つの製品について、ベンダーに直接ヒアリングを行った結果、BIZXIM製番の導入を決定しました。決め手となったのは、私たちが提示した様々な要件に対して、どこまで標準機能で対応できるのか、あるいはカスタマイズや追加開発が必要になるのかといったことが明確で、生産管理システムの“形”が確実に見えたことです。
BIZXIM製番の導入スケジュールは?
- 山崎氏
プロジェクトのキックオフから実質3か月半ほどの短期間でフィット&ギャップフェーズを終えることができました。この成功に大きく貢献したのは、NTTデータ関西による各製造現場の主要メンバーを巻き込んだきめ細かいサポートです。
システム導入の早い段階からアセスメント環境を用意していただき、実務に近い仮データを投入して実際の画面上で操作を行うなど、新システムの動作イメージをユーザー自身に掴んでもらいながら基本設計を進めていきました。- 石井氏
また、NTTデータ関西には新システム稼働開始後も本番環境とは別に、自由にデータを投入してシステムの様々な動作を検証できるテスト環境を用意していただいています。おかげで新システムのマニュアル作成がスムーズに進みました。さらにこのテスト環境は、各製造現場から寄せられる様々な問い合わせやサポート依頼への対応にもとても役立っています。
本番運用開始後に得られた導入効果は?
- 山崎氏
最大の効果は、データドリブンによる製造現場の業務改革が大きく前進したことです。具体的にはバーコードを通じて工程間でデータを受け渡すとともに、そのデータを全社で共有できるようになりました。
例えばある製品の生産が、現時点でどれくらい進捗しており、何台完成したのかといった状況を一元的に把握・管理し、必要に応じて手を打つことが可能となりました。以前のように頻繁に現場に足を運んで状況を確認したり、無駄な問い合わせをしたりする必要はなくなりました。- 吉川氏
IT部門としても困難だった保守メンテナンス業務から解放され、作業負担は大幅に軽減されています。BIZXIM製番の基本的な管理は、すべてNTTデータ関西側で行われているため運用も安心です。私たちは業務目線に立ったユーザーサポートに徹することが可能となりました。
BIZXIM製番を活用した今後の展望は?
- 山崎氏
今後に向けて取り組みを強化しようとしているのは、M-BOM(製造部品表)の活用です。
実は現時点ではBIZXIM製番にはE-BOM(設計部品表)しか反映できていないため、当初からの目標としていた受注から出荷までトータルに見渡すことができる生産管理システムにはまだ至っていません。E-BOMとM-BOMを緊密に連携させたデータ活用によって、製造現場の視点による必要な部品や資材の調達、工程情報の管理、生産計画、生産指示、出荷指示などを、可能な限り早期に目標を達成したいと考えています。
もっとも簡単なテーマでないことは、重々に承知しています。技術的にも非常に高度な知見が要求されるため、私たちが自力で実現するのは困難であり、その意味でもNTTデータ関西には引き続き親身なサポートを期待しています。